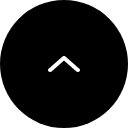本文
井原市(いばらし)ゆかりの偉人(いじん)
井原市ゆかりの偉人
北条早雲(ほうじょうそううん)
備中国(びっちゅうのくに)高越山城主(たかこしやまじょうしゅ)伊勢盛定(いせもりさだ)の子として荏原庄(えばらのしょう)に生まれ、幼少期(ようしょうき)から青年期に(せいねんき)かけて当地で過ごしたといわれます。室町幕府(むろまちばくふ)将軍(しょうぐん)足利義政(あしかがよしまさ)の弟、足利義視(あしかがよしみ)に仕え、応仁の乱(おうにんのらん)の後、駿河守護(するがしゅご)の今川義忠(いまがわよしただ)に嫁(とつ)いでいた妹を頼って駿河におもむきました。今川家の家督(かとく)争いの仲裁(ちゅうさい)で頭角(とうかく)をあらわし、その後、今川家や扇谷上杉家(おうぎがやつうえすぎけ)の下で勢力(せいりょく)を拡大(かくだい)しつつ、晩年(ばんねん)には相模全域(さがみぜんいき)を統一(とういつ)しました。家法(かほう)を定め、検地(けんち)を行うなど領国(りょうど)の拡大と支配(しはい)の強化を積極的(せっきょくてき)に進めたことから、最初の戦国大名(せんごくだいみょう)とも呼ばれています。

那須与一(なすのよいち)
源平合戦(げんぺいがっせん)の英雄(えいゆう)として知られる那須与一。那須氏は、源氏(げんじ)に仕えた関東武士で、与一は源平合戦において源義経(みなもとのよしつね)に従軍(じゅうぐん)し、屋島(やしま)の戦いで平氏方(へいしがた)の舟上(せんじょう)にかかげられた扇(おうぎ)の的(まと)を射落(いお)としたことで、一躍(いちやく)歴史に名をとどめました。
後に与一は、合戦での功績(こうせき)から備中荏原庄(びっちゅうえばらのしょう)など全国5ヶ所の地頭職(じとうしき)を賜(たま)わりました。市内には、与一が屋島の合戦で弓を引く際に破り捨てた片袖(かたそで)を祀(まつ)ったという袖神稲荷(そでがみいなり)、那須氏の菩薩寺(ぼだいじ)の永祥寺(えいしょうじ)や与一の墓(はか)など与一ゆかりの史蹟(しせき)が今も残っています。

雪舟(せっしゅう)
雪舟は総社市(そうじゃし)赤浜(あかはま)に生まれたと伝えられ、京都・相国寺(しょうこくじ)に入ってから周防国(すおうのくに)にうつった後、遣明使(けんみんし)に随行(ずいこう)して中国に渡り、中国の水墨画(すいぼくが)を学びました。作品数は多く、中国風の山水画(さんすいが)だけでなく人物画(じんぶつが)や花鳥画(かちょうが)もよくしました。「東福寺誌(とうふくじし)」や「吉備物語(きびものがたり)」などの文献(ぶんけん)によれば、雪舟は芳井町の重玄寺(ちょうげんじ)で亡くなったとされていますが、雪舟の生涯には謎が多く、終焉(しゅうえん)の地についても山口市雲谷庵(うんこくあん)、益田市(ますだし)大喜庵(たいきあん)などの説もあります。
しかし、重玄寺には雪舟作と伝えられる「緋衣達磨像(ひえだるまぞう)」など画幅(がふく)が数点残されており、また平成8年には雪舟と重玄寺を開いた千畝和尚(せんみょうおしょう)とを結びつける資料「也足外集(やそくげしゅう)」が発見され注目されています。

平櫛田中(ひらくしでんちゅう)
平櫛田中は、後月郡(しつきぐん)西江原村(現・西江原町)に生まれ、平櫛家の養子(ようし)になった後、大阪の人形師・中谷省古(なかたにせいこ)の下で木彫(きぼり)の修行(しゅぎょう)をしました。後に上京して高村光雲(たかむらこううん)を訪ねましたが、独学(どくがく)により修行を続け、明治末期から大正初期にかけて岡倉天心(おかくらてんしん)に師事(しじ)し、写実的(しゃじつてき)な作風(さくふう)で日本近代を代表する彫刻家(ちょうこくか)の一人になりました。
1944年(昭和19年)から東京美術学校(現・東京芸大)の教授(きょうじゅ)となり、1958年(昭和33年)には代表作「鏡師子(かがみじし)」を完成、1962年(昭和37年)には、文化勲章(ぶんかくんしょう)を受章(じゅしょう)しました。
100歳を超え長命(ちょうめい)でしたが、死の直前まで創作(そうさく)を続けました。また、田中は美術書をはじめ、漢籍(かんせき)、仏典(ぶってん)、哲学書(てつがくしょ)など万巻(まんがん)の書物を読破(どくは)した大読書家(だいどくしょか)でもあり、自己の感懐(かんかい)や抱負(ほうふ)を述べた名言(めいげん)・名句(めいく)を墨書(ぼくしょ)して残し、今も人々の心をとらえつづけています。

内山完造(うちやまかんぞう)
内山完造は、後月郡(しつきぐん)吉井村(現・芳井町吉井)に生まれました。12歳の時、大阪へ丁稚奉公(でっちぼうこう)に出た後、京都の商家(しょうか)で10年間働きましたが、キリスト教京都教会の牧野虎次牧師(まきのとらじぼくし)(後の同志社大学総長)の紹介(しょうかい)で28歳の時、大学目薬(だいがくめぐすり)参天堂(さんてんどう)の上海出張員(しゃんはいしゅっちょういん)として中国に渡ります。そして、1917年(大正6年)、上海に内山書店を開業しました。内山書店には、魯迅(ろじん)、郭沫若(かくまつじゃく)、谷崎潤一郎(たにざきじゅにちろう)、佐藤春夫(さとうはるお)、林芙美子(はやしふみこ)ら日中の知識人が頻繁(ひんぱん)におとずれ、サロンを形成(けいせい)しました。日本の大陸進出に対する反日(はんにち)・抗日運動(こうにちうんどう)の中においても、完造は幅広く中国人と友情を結び、戦後は日中友好協会(にっちゅうゆうこうきょうかい)の初代理事長(しょだいりじちょう)に就任(しゅうにん)するなど、日中友好・国交回復(こっこうかいふく)のために力をつくしました。
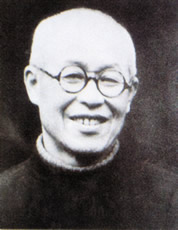
阪谷郎廬(さかたにろうろ)
阪谷郎廬は、備中国(びっちゅうのくに)川上郡九名村(くみようむら)(現・美星町明治)に生まれました。大坂、江戸で漢学(かんがく)を学んだ後、帰郷(ききょう)して伯父(おじ)の山鳴大年(やまなりだいねん)の勧(すす)めで1851年(嘉永:かえい4年)に芳井町簗瀬(やなせ)に桜渓塾(おうけいじゅく)を開きました。若者達(わかものたち)の人材育成を目指した漢学塾(かんがくじゅく)です。桜渓塾には、全国各地から郎廬を慕(した)う漢学者・志士(しし)たちが集まりました。1853年(嘉永6年)には一橋(ひとつばし)江原役所が地元の有志(ゆうし)の拠金(きょきん)を得て設立した教諭所(きょうゆじょ)に教授として招かれ、教諭所を「大学」に出典を求めて「興譲館(こうじょうかん)」と命名(めいめい)し、初代館長に就任(しゅうにん)しました。その後も1868年(明治元年)まで15年間子弟(してい)の育成にあたり、郷土(きょうど)はもとより近代日本の発展(はってん)に貢献(こうけん)した有能(ゆうのう)な人材を多く輩出(はいしゅつ)しました。