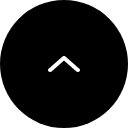本文
井原市(いばらし)の自然(しぜん)
井原市の自然
経ヶ丸山頂(きょうがまるさんちょう)
標高(ひょうこう)281メートル。周囲(しゅうい)のみはらしがよく、北に高梁市(たかはしし)の弥高山(やたかやま)、西に福山市(ふくやまし)の工業地帯(こうぎょうちたい)、沖に停留(ていりゅう)する船が見え、南には笠岡沖(かさおかおき)、東に水島(みずしま)の工業地帯(こうぎょうちたい)がみわたせます。正月には初日の出(はつひので)を見るために多くの人でにぎわいます。

浪形岩(なみがたいわ)
標高(ひょうこう)約260メートル、千手院(せんじゅいん)の庭に露出(ろしゅつ)した貝殻石灰岩(かいがらせっかいがん)で、岩はだが長い年月の間に地下水で溶(と)かされ、そのあとが、浪(なみ)に洗われたあとのように見えることから「浪形岩」と呼ばれています。
この石灰岩は、カキ、ハネガイ、ベンケイガイなどの貝類の化石から形成(けいせい)されていて、まれに、サメの歯、ウニの化石も見られます。
時代は、中新世(ちゅうしんせい:約2000万年前)で、当時このあたりが浅い海であったことがわかります。幕末(ばくまつ)に、千手院の住職(じゅうしょく)証算和尚が庭をほり出したことにより、現在、すばらしい景観(けいかん)をおりなしています。

道祖渓(どうそけい)
全国的にもめずらしい輝緑岩(きりょくがん)の渓谷(けいこく)。小田川(おだがわ)の支流(しりゅう)雄神川(おがみがわ)にあり、輝緑岩の台地を深くけずって那須氏(なすし)の菩提寺(ぼだいじ)・永祥寺(えいしょうじ)の南へ流れ出ます。永祥寺を初めて開いた実峰良秀(じっぽうりょうしゅう)をしたい集まった童子(どうじ)の中に道祖神(どうそじん)の化身(けしん)がいたという伝説(でんせつ)から「道祖渓」と命名(めいめい)されました。

鳴滝峡(なるたききょう)
およそ800メートルの遊歩道(ゆうほどう)の中に大小さまざまな11の滝からなる山間の美しい渓谷(けいこく)です。鳴滝(雄滝:おだき)と二ノ滝が、まるで1つの滝であるかのように見える中ほどの展望台(てんぼうだい)からのながめが最高です。河床(かしょう)には甌穴群(おうけつぐん)や切り立った屏風岩(びょうぶいわ)を見ることができます。

天神峡(てんじんきょう)
天神峡は四季折々(しきおりおり)に美しい姿をみせます。天神社(てんじんしゃ)・黒丸神社(くろまるじんじゃ)の社叢(しゃそう)を中心とした小田川に沿った景勝地(けいしょうち)で、高梁川上流(たかはしがわじょうりゅう)県立自然公園の中にあります。渓谷(けいこく)は1キロメートルにわたり、カエデ・モミ・カシなどの巨樹(きょじゅ)・老木(ろうぼく)が清流(せいりゅう)に影を落とします。

鬼ヶ嶽(おにがたけ)
鬼ヶ嶽は美山川(みやまがわ)の上流の浸食(しんしょく)された輝緑岩(きりょくがん)の地盤(じばん)と水辺(みずべ)の樹層(じゅそう)が約4kmにわたって続く渓谷で、周辺には遊歩道も整備されています。新緑(しんりょく)の春、カジカガエルの鳴き声が響き、ホタルが飛び交う初夏(しょか)、紅葉(こうよう)に包まれる秋、渓谷が雪化粧(ゆきげしょう)する冬など、四季折々(しきおりおり)の豊かな表情を見せてくれます。

白糸の滝(しらいとのたき)
白糸の滝は、その名のとおり流れる水が、まるで白い糸のように美しい滝です。滝は5段になっており、5段合わせて落差(らくさ)は25メートルあります。その流れは美山川(みやまがわ)へと流れ込みます。周辺には新たに桜やもみじ約350本が植えられ、桜や紅葉の時期には滝の美しさとあいまって格別(かくべつ)に美しい景観(けいかん)を見せます。