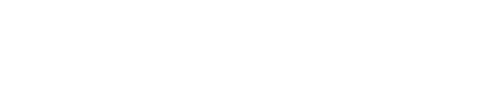本文
田中こぼれ話
田中こぼれ話 その1
田中が、百歳の祝賀パーティーであいさつに立ったとき、「どうか皆さん、あまり私のところを訪問しないでください。私はまだ制作もしたいし勉強もしたいので、ご好意に甘えるならば、どうか仕事の邪魔をしないでください。」とユーモアを交えながら話しました。
百歳を迎えてもなお制作意欲は盛んでした。800人ほどいた聴衆は納得し、微笑みうなずきました。その後、田中宅の訪問者はめっきり少なくなったそうです。
田中こぼれ話 その2
田中は、大作「鏡獅子」を作成するとき、モデルの六代目菊五郎が公演している歌舞伎座に、25日間通いつめ、いろいろな角度から舞姿を観察しました。そして、納得のいくまで構想をねっています。
モデルを見つめるときの田中の目のすわり、着眼の厳しさ、的確さは、「まるで踊りの名人の目だね」と菊五郎が語ったといいます。
田中こぼれ話 その3
晩年の田中は、趣味で硯を集めていましたが、死んだら孫や弟子への形見わけにしようと思っていました。奈良へ行った時、道具屋が端渓の石材を1個5万円のところを5個で10万円にするというので、買って帰りました。ところがあとで専門家に見てもらったところ、素人にはほとんど見分けのつかないにせ物だと分かりました。田中は「えらいことをやるもんだねえ」と感心し、少しも不快な顔はしませんでした。うまい仕事には無条件に敬服する人でした。
田中こぼれ話 その4
田中はそれまでのアトリエが手狭になり、大作を作る場所がなく困っていると、同じ日本美術院同人の横山大観・下村観山・木村武山が「平櫛さん、アトリエを作る費用はなんとかするから、良い作品を作ってください」と言って自分たちの絵を売り、それを資金にアトリエを建ててくれました。上野桜木町のアトリエは、3巨匠からの温かい友情の贈り物です。
田中こぼれ話 その5
昭和44年、今の井原市民ギャラリーが田中館として開館したとき、田中が、楠木の若木を記念植樹しました。一鍬一鍬土をかけながら、「枯れなよ、大きくなれよ、千年も万年も生きよ」と唱えるようにつぶやきながら、土をかぶせました。田中は仕事に対しては厳しい人でしたが、どんなものに対しても深い愛情を持ち、優しい心遣いをする人でした。
田中こぼれ話 その6
平櫛田中は昭和37(1962)年、文化勲章を授与され、木彫界の最高峰として認められました。伝達式の日、田中は他の受章者とともに皇居に招かれました。
天皇陛下は一人一人に親しく声をかけられ、田中には「あなたが一番苦心されたことは、どんなことですか」と、たずねられました。田中は「それは、おまんまを食べることでした」と答えました。
この言葉は田中の一生を象徴していると言えます。彫刻界という恵まれない分野で苦闘してきた田中だからこそ、実感をもって口にすることができたといえます。
田中こぼれ話 その7
明治の初め、仏教信仰が下火になり仏像の必要性が減ってきました。それはすなわち、木彫界の衰退を意味するもので、彫刻で暮らしをたてることは難しくなっていました。
木彫家を志す人たちがいつも悩んでいたことは、どのようにすれば作品が売れるようになるだろう、ということでした。
田中の仲間の一人が岡倉天心に、彫刻が売れるようにするにはどうすればいいか、と尋ねると「みんなは売れるようなものを作ろうとする。だから、売れないのです。売れないものを作りなさい。そうすれば、必ず売れます」と答えました。その言葉を聞いて田中は、他人の作品がどうであれ、自分が作りたいものを作ることが一番大切なのだ、と気付きました。
田中こぼれ話 その8
岡倉天心は明治を代表する思想家であり、田中が活躍の場としていた日本美術院を創立した人です。田中はその天心に師事していました。天心が亡くなった後、田中はポーズのちがう天心像を、その時々に制作しています。
その中の一つに東京美術学校から依頼され制作したものがあり、現在でも東京芸大(前東京美術学校)の木立のなかの六角堂に安置されています。田中が東京美術学校の教授になったのは昭和19年、72歳になってからでしたが、この天心像を制作したのは昭和6年でした。正木校長が退官する際、初代校長の天心の像を是非残しておきたいということで、短い間でしたが直接教えをこい、天心を知っている田中に作ってほしいと依頼がありました。
田中は教授をしているとき、学校に着くと毎朝、天心像の前で最敬礼していました。天心の死後、何十年経ってもこの様な光景が見られ、一日として師の恩を忘れたことのない田中の姿がそこにはありました。
田中こぼれ話 その9
田中には3人の子供がいて、長女・幾久代、長男・俊郎、次女・京子といいました。
大正14年、3人が相次いで肺結核になり、翌年春、幾久代の容態が悪化したため、療養のため神奈川県平塚に家を借り、田中は看病に精を出しました。いっこうによくならない幾久代のために、田中は快復の願いをこめて「大日如来香合仏」を彫り、福山市の菩提寺・善立寺に奉納しました。
しかし、そのかいもなく大正15年、幾久代は19歳の若さでこの世を去りました。
俊郎は幾久代の後を追うようにして亡くなっていますが、死ぬ間際に「お父さん、仕事は上手にならなくてもいいから、わたしの分まで長生きして、たくさんの作品を作ってください」と言い残しています。
田中こぼれ話 その10
田中が約20年間かけて制作した大作「鏡獅子」が完成した昭和33年ごろ、東京の三宅坂に国立劇場が作られることになりました。
この新しい劇場に「鏡獅子」を飾るとふさわしいだろう、と国が2億円で買い上げようとしましたが、「お金はいりません。この作品は私一人で作ったものではなく、六代目菊五郎さんと2人でこさえたもんです。お金をとったら、あの世で六代目さんに会ったとき、あいさつのしようがないですよ。」田中はこう答えて、東京国立近代美術館に寄贈し、近代美術館はこの作品を国立劇場に貸すことにしました。
こけらおとしの日、国立劇場の正面にすえられた大作を見つめる人々は圧倒され、いつまでも動こうとしませんでした。
田中こぼれ話 その11
田中は大作鏡獅子を院展に出品した後、気に入らないところを直すためアトリエに持ち帰っていました。
ある晩、東京を台風が襲いました。当時のアトリエはお花茶屋にあり、低地なため台風が来るとたいてい水に浸かってしまう場所でした。田中は一晩まんじりとも出来ず心配しました。
翌朝、電車は一駅手前までしか通っていませんでしたので、そこからは線路づたいに腰までつかって歩きました。そしてアトリエにある大事な作品は、水面より高いところに置いてあり無事だったのを見て、やっと安心して帰ったというエピソードがあります。田中88歳の話です。