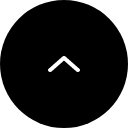本文
【注意喚起】麻しん(はしか)の感染事例が国内で増加しています!
令和7年3月19日現在、麻しん(はしか)の国内外での感染報告数がさらに増加しています。特に、ベトナムをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しており、今後、輸入事例の更なる増加や、国内における感染伝播事例が増加することが懸念されます。
これらの状況を踏まえて、海外渡航する方は下記を参考にして感染に注意しましょう!
▼厚生労働省HP▼
麻しんについて<外部リンク>
▼麻しんの予防接種に関する啓発リーフレット▼
麻しん(はしか)はワクチン接種が予防に有効です!<外部リンク>
海外渡航者の方へ
海外渡航の予定がある方は、次のことに注意しましょう!
・ウェブサイト等を参考に、渡航先の麻しんの流行状況を確認しましょう。
・母子健康手帳などを確認し、過去の麻しんに対する予防接種歴、り患歴を確認しましょう。
・過去定期接種を実施した記録がない場合は、渡航前に予防接種を受けることを検討しましょう。
・麻しんのり患歴やワクチン接種歴が不明な場合は、抗体検査を受けることを検討しましょう。
渡航前に読むリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/519KB]
麻しんの流行がみられる地域に渡航した方は、次のことに注意しましょう!
・渡航後、帰国後2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意しましょう。
・発熱や咳そう、鼻水、目の充血、全身の発しん等の症状が見られた場合は、医療機関を受診しましょう。また受診時には、医療機関に対して事前に、麻しんの流行がみられる地域に渡航していたことや、麻しんの可能性について伝えましょう。
・医療機関を受診する際には、医療機関の指示に従うとともに、可能な限り公共交通期間を用いることなく受診しましょう。
渡航後に読むリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/519KB]
麻しん(はしか)はどんな病気?
麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。
感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。
2~3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。
肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。
死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。
その他の合併症として、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することもあります。
麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播し、その感染力は非常に強いと言われています。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。
発疹、発熱などの麻しんの症状がある場合
ワクチンを2回接種したことがない方やこれまで麻しんに罹患したことがない方は、感染するリスクがあります。
麻しんの疑いがあることをかかりつけ医や医療機関に電話等で伝え、受診の要否等を確認してからその指示に従ってください。また、麻しんの感染力は非常に強いと言われています。
医療機関へ移動される際は、周囲の方への感染を防ぐためにもマスク着用し、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。
麻しん(はしか)はワクチン接種が予防に有効です!
定期接種時期に、麻しん風しん混合(MR)ワクチンをなるべく早く接種しましょう。
1回目:生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある幼児が対象
2回目:小学校就学前の1年間、幼稚園、保育所等の最年長クラス児童が対象
また、定期接種の時期にない方で、「麻しんにかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことがない方」は、かかりつけの医師にご相談ください。
麻しん含有ワクチン(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%程度の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。
また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった方の多くに免疫をつけることができます。
◎麻しん含有ワクチンは、ニワトリの胚細胞を用いて製造されており、卵そのものを使っていないため
卵アレルギーによるアレルギー反応の心配はほとんどないとされています。
しかし、重度のアレルギー(アナフィラキシー反応の既往のある人など)のある方は、ワクチンに含まれるその他の成分によるアレルギー反応が生ずる可能性もあるので、接種時にかかりつけの医師に相談してください。