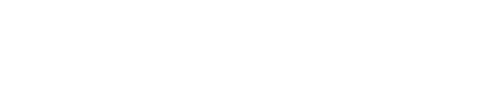本文
活人箭


- 活人箭(かつじんせん)
- 1969年(昭和44年)
- 木彫
田中は彫刻家を志し26歳で上京してから、西山禾山和尚の禅の提唱を聞くきっかけを得ます。禾山和尚は、難解な仏教の教えをやさしく説いたため、たくさんの人が参禅しました。この作品は、その時聞いた話に取材しています。田中は、米原雲海らと結成した日本彫刻会の第1回展にこの活人箭を出品しますが、その時は弓矢をつがえていました。しかし、それを見た岡倉天心に、そんなことでは死んだ豚も射れまい、彫刻の力だけで表現してみなさい、と教えを受け弓矢を取り外して作品を仕上げています。
このはりつめた禅機(禅の修行によって体得した無我の境地から出る心のはたらき)の表現が、天心の目にはっきりと田中の存在を焼き付けることになります。天心は、芸術の表現は理想にあるとよくいっていましたが、その理想をやってくれる彫刻家は田中だけだと語ったといいます。